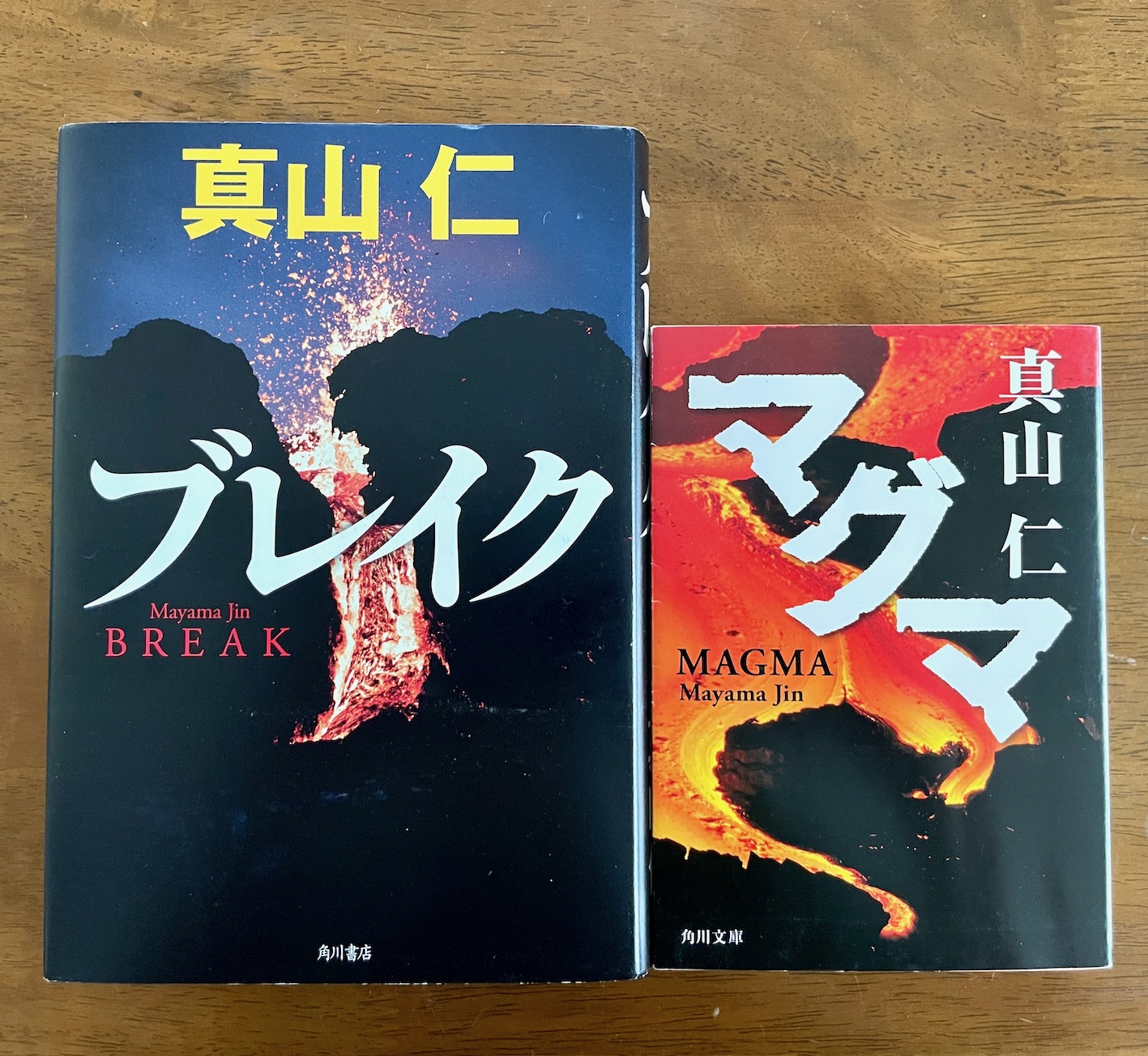2050年のカーボンニュートラルに向けて、2030年代には実用化が望まれる「次世代型地熱技術」について、課題や開発・実証スケジュール等具体的な目標・計画を官民が一体となって議論・策定する協議会が、4月14日に開催された。
そこで話題となったのが、「クローズドループ」だ。
高温の地熱層にパイプを通し、水を循環させて発生した蒸気でタービンを回す仕組みで、熱源として高温の貯留層を必要としないこと、従来型よりも広範囲の地熱資源が活用可能であることが評価されている。
また、掘削コストの低減にもつながり、一気に事業化が加速する可能性を秘めている。中部電力は海外の事業者に出資し、ドイツで世界初の商業運転を目指しているという。
しかし、パイプに注入した水を高温にするだけの熱源は必要であり、採熱量には物理的な限界がある。新しい技術なだけに、慎重になるべき点もあるのではないか。長年、地熱発電開発の実態を研究・調査してきた、安川香澄氏(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 特命参与)は以下のように課題を指摘する。
「クローズドループの考え方は、実は1970年代からありました。ただ、残念ながら、採熱すると、パイプ付近の岩盤の温度が急激に下がり採熱量が激減してしまいます。岩盤の熱伝導率が低いため、パイプ付近が冷えるだけで周囲の温度はそのままに保たれ、広い範囲から熱を取ることができません。計算結果によれば、従来の地熱発電に比べ、数十倍~数百倍もの長さの孔を掘削する必要があり、経済性がないと見られてきました。
実際、近年進められているドイツでのプロジェクトでも、最初は地熱発電+熱供給という触れ込みで既に発電機も購入したそうですが、何かと遅延が続いており、まずは熱供給のみとなるのではないでしょうか。
クローズドループ関連で新しい技術と言えるのは、水平方向の掘削が可能になった点だけです。しかし日本への応用では、鉛直断層が多いため水平方向の掘削という工事自体が極めて難しいという問題もあります。
また、技術開発により掘削費が下がったという米国での研究成果がありますが、燃料費や人件費の高騰で掘削費が上がる要素の多い中、けた違いに下がる可能性はまず無いでしょう。」
クローズドループ開発がバラ色の未来につながるという安直な発想ではなく、従来型技術の運用および他の次世代型地熱技術の開発にも注力していくよう、偏りなく可能性を広げられるよう、協議をすすめてもらいたいものだ。
(※5月7日に一部原稿を修正した)
【参考資料】
「次世代の地熱発電技術を官民で開発へ…「クローズドループ」2030年代の実用化目指す」(「読売新聞」2025年4月14日)
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250414-OYT1T50004/
「次世代型地熱、10月に工程表/エネ庁、官民協議会が始動」(「電気新聞」2025年4月15日)
https://www.denkishimbun.com/archives/385248
プロフィール:
柳田京子
真山仁事務所スタッフ。フリーランスの編集・ライター。